みなさんは一日の中でどのくらい甘いものを口にしますか?また子どもにどのくらい甘いものを食べさせて(飲ませて)いますか?甘いものを摂取することによって引き起こされる弊害はたくさんあるようですが、かといって甘いものを食生活から完全に断ち切ることも不可能に近いことと思います。今回は日常の食生活でどのように、またどのくらいの目安で甘いものを食べたら良いのかを探ってみました。
まず私たちが普段よく口にする甘いものにどのくらいの砂糖が含まれているかをざっと調べてみました。
ヤクルト(10g)、アイスクリーム(30g)、マックシェイクMサイズ(70g)、ポカリスエット500ml(30g)、ビスコ1パック(14g)、あんぱん(20g)、フルグラ(6g)
意外なものに多くの砂糖が含まれていて少し驚いたものもありますが、総じて飲み物に大量のお砂糖が使われているようですね。調べてみて気づいたのですが食品の成分表を見てもお砂糖の量はぱっと見てもどこに記載されているのかわかにくいのですが、成分表に書かれている「炭水化物」=糖類+食物繊維、ということで、それが飲み物であれば炭水化物=糖類、と判断して良いようです。
次に私たちが一日でどのくらいの糖分を摂取したらよいのかを調べてみました。WHO(世界保健機関)のガイドラインでは、成人及び児童の1日当たりの糖類の摂取量をエネルギー総摂取量の10%未満に減らすことを推奨しており、さらに5%(1日25g/ティースプーン6杯分)程度に抑えることができれば、より健康効果が高まる、ということです。
最後は甘いものの摂り方ですが、虫歯の観点から見れば口の中が常に甘いもので満たされている状態がもっとも虫歯になりやすいので、頻繁に飴をなめたり甘いものを飲んだりすることが一番いけないようです。少なくともお口の中で「再石灰化」(酸で傷ついた歯が唾液の働きで修復される現象、食後30分~1時間で始まる)されるまでは次の甘いものを口の中に入れない方が良さそうです。
また甘いものを食べることで起きる血糖値の上昇を抑えるインスリンの働きも体の中にある体内時計と連動しているので、食事の時間を規則正しくすることでより効果が期待できるようです。 普段の生活ではジュースをお茶に変えるなどして、お祝い事などの特別な日には美味しいケーキやお菓子をみんなで楽しくいただく。甘いものとはそんな付き合い方がベストなように思います。
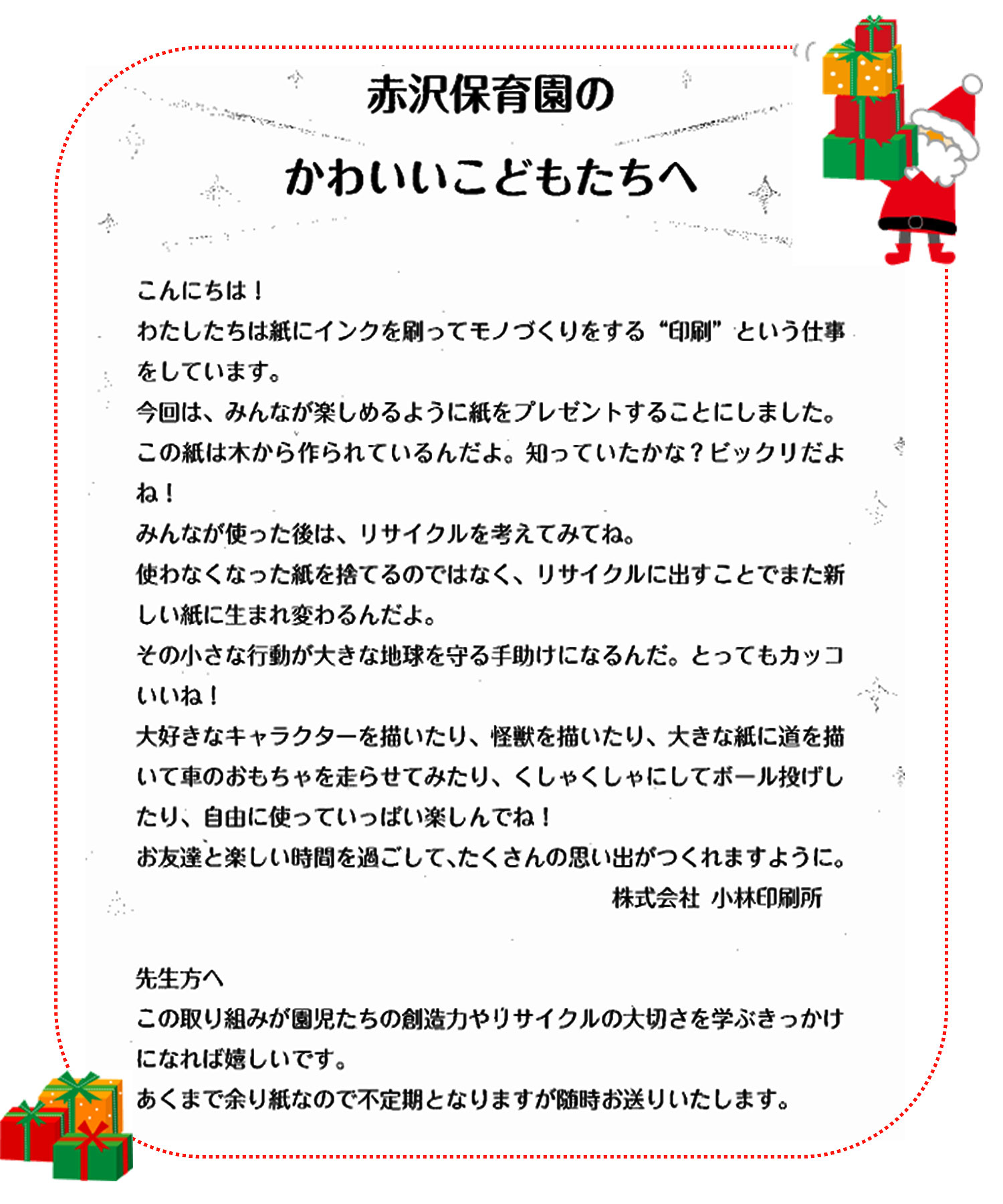
 ←「読解問題よみとくん」
←「読解問題よみとくん」